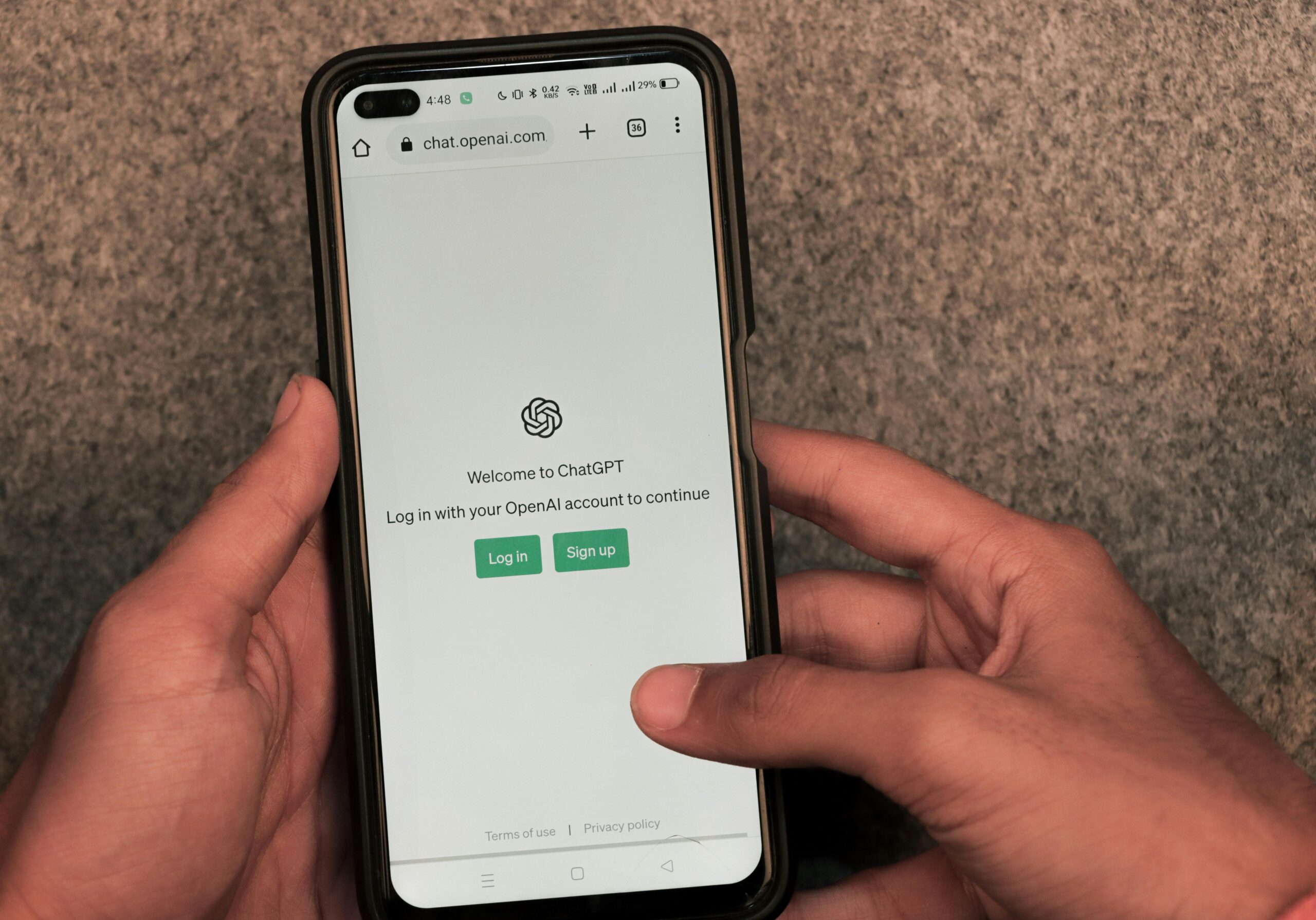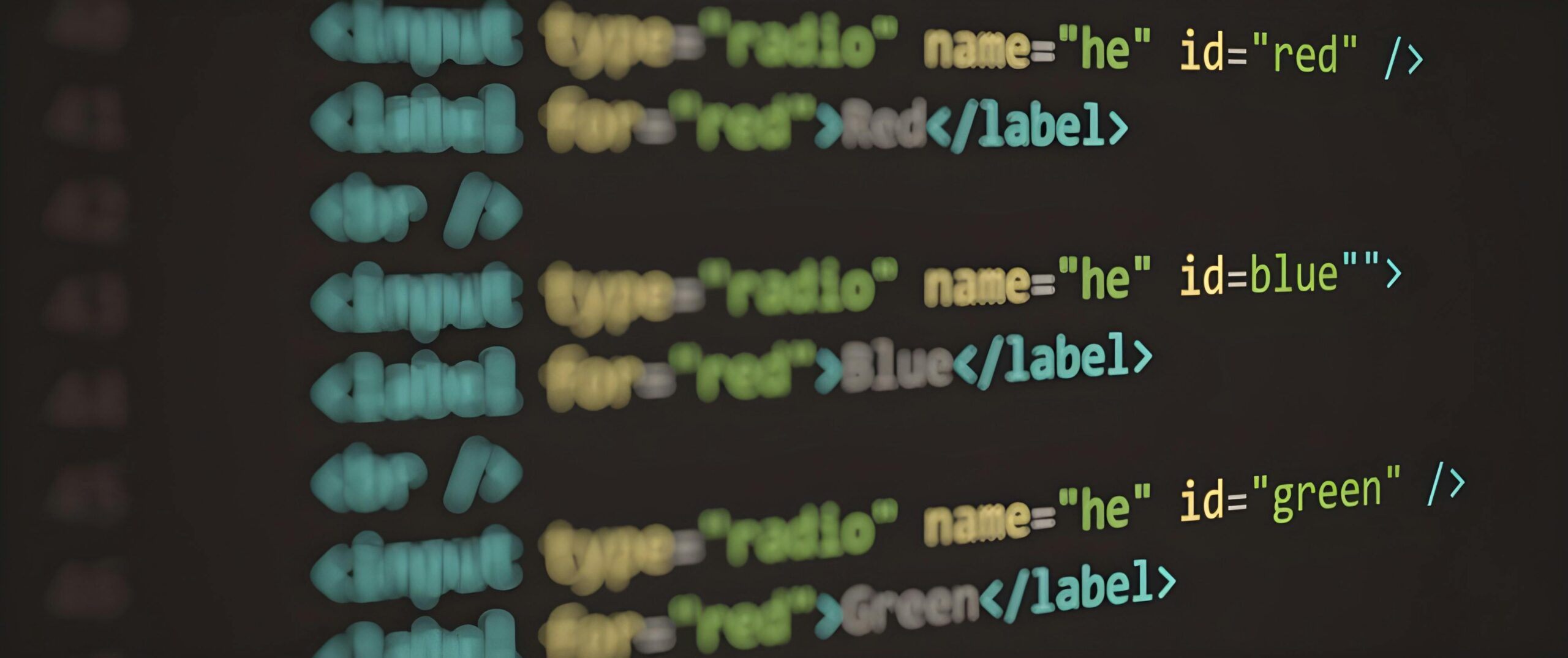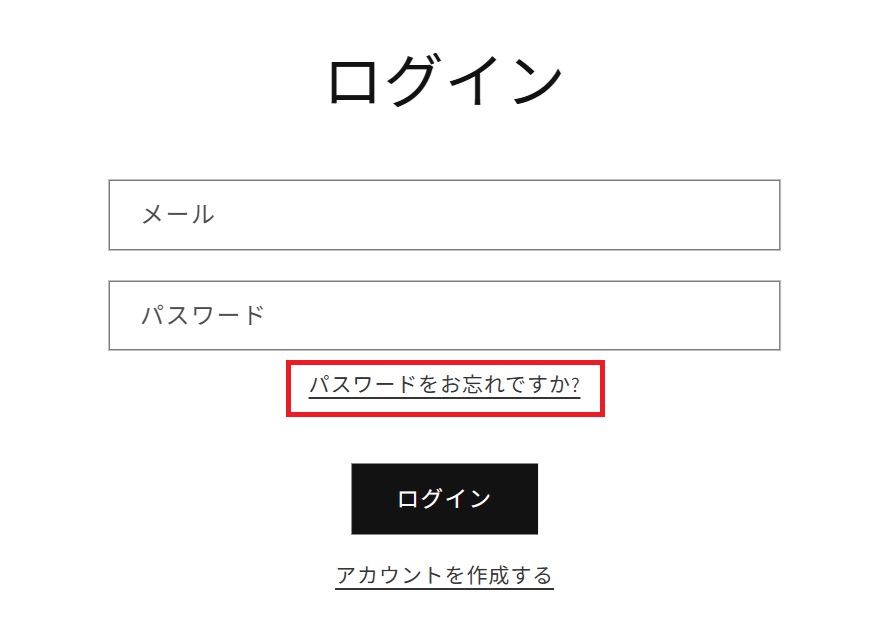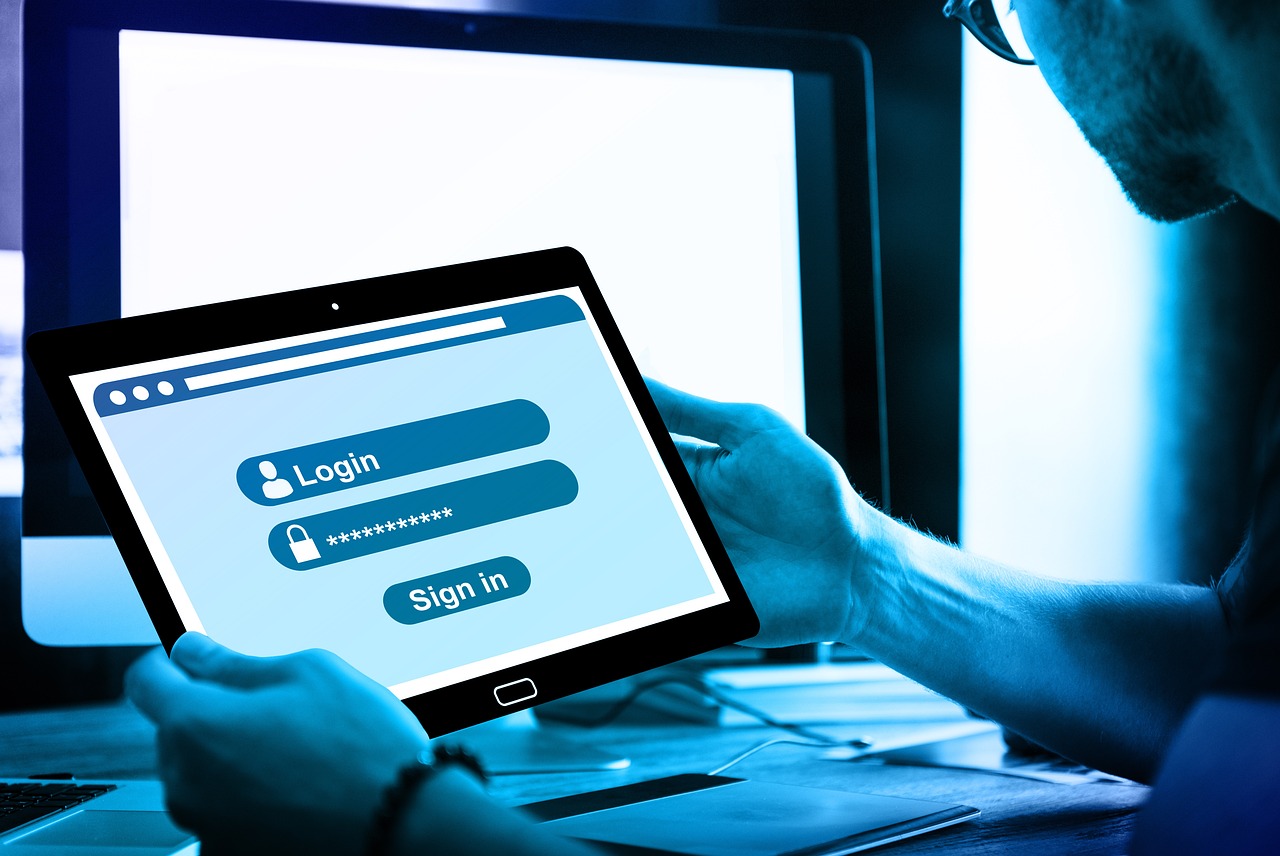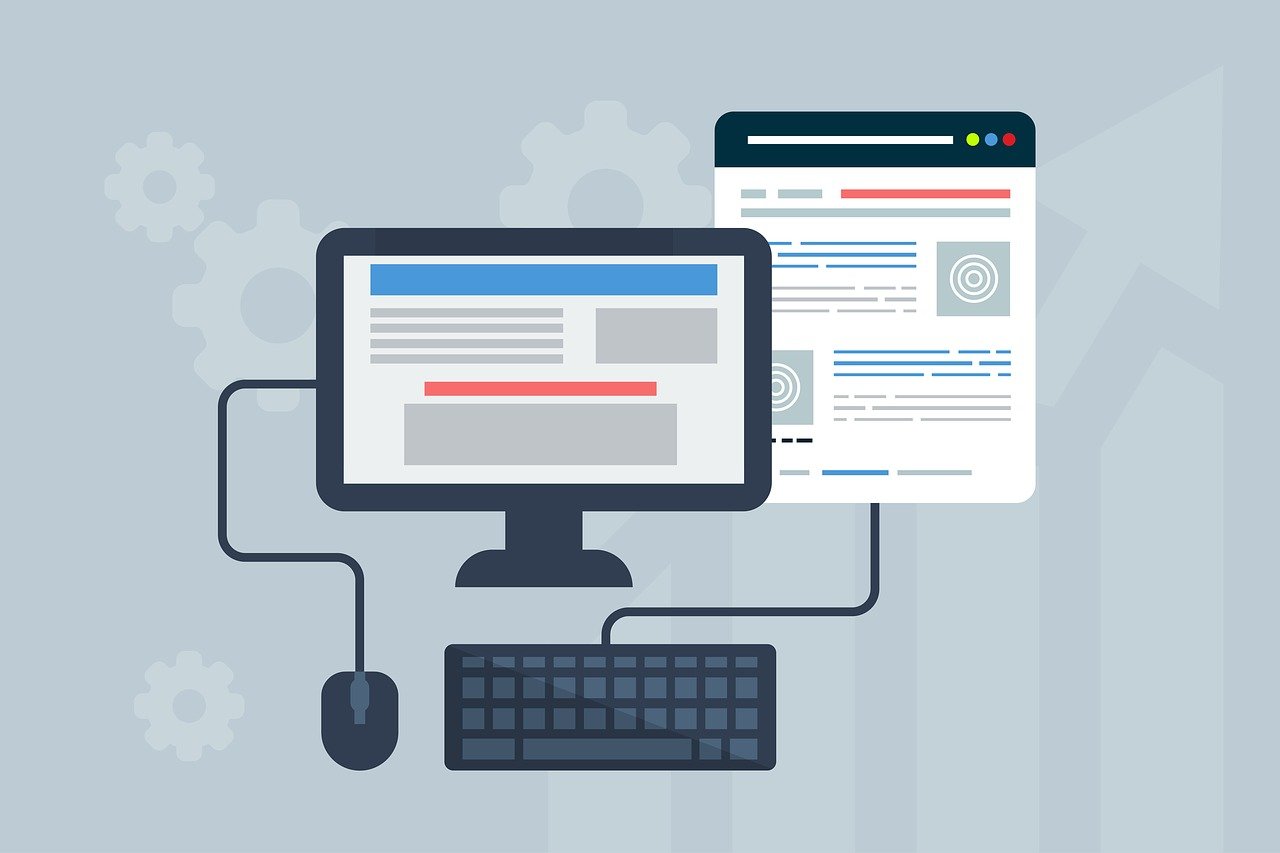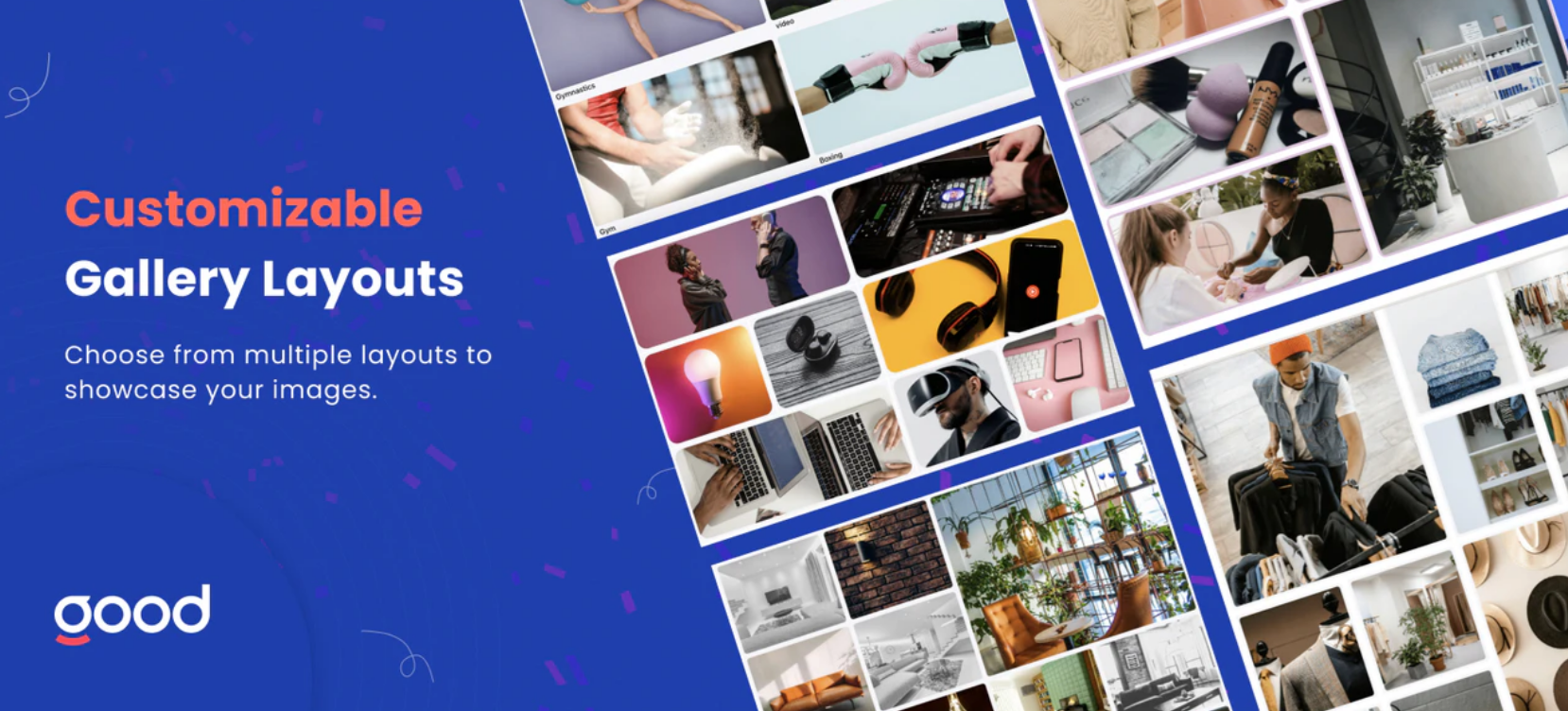挑戦をあきらめてしまう最大の原因は「最初の失敗」だと感じていたが、鳥の巣が頑丈になる仕組み――ジャミング現象――を知り、試行錯誤こそが成功の構造を築くために必要なプロセスだと気づいた。初期の失敗は、成果を支える“見えない土台”かもしれない。

こんにちは、ブログ管理人のホリです。
挑戦って、言葉では軽く聞こえるけど、実際にやってみるとかなり重いものですよね。
個人的には、挑戦が挫折に変わる最大の理由は「最初の失敗」なんじゃないかと思っています。
新しい分野に飛び込むときって、必ずと言っていいほど“うまくいかない瞬間”にぶつかります。
そのときに感じる痛みが予想以上に強くて ―― 気がつくと「やっぱり無理だったか」「うまくいくわけないよな」と、あきらめてしまう。
そんな経験、ありませんか?
私自身も、何度となくそういう感情に引き戻されそうになったことがあります。
でも最近、「失敗はプロセスそのものなんだ」と感じさせてくれる、ある面白い研究に出会いました。
鳥の巣は、なぜあんなにも頑丈なのか?
「なぜ鳥の巣はあんなにしっかりしているのだろう?」
そんな素朴な疑問から始まったのが、アメリカ・アクロン大学のハンター・キング(Hunter King)教授の研究です。
彼のチームが注目したのは、巣作りに使われる“細い枝”たち。
実験と観察を繰り返すなかで、彼らはひとつの現象にたどり着きました。
それが「ジャミング(Jamming)現象」です。
これは、細い枝やパーツがある一定量以上積み重なると、お互いに絡み合いながら固定され、やがて1本を動かすにも構造全体に力を加えないと崩れないほど、頑丈な構造が自然に生まれるという現象です。
最初のうちは、どれだけ枝を積み重ねてもすぐに崩れてしまう。
でも、ある“しきい値”を越えると、一気に安定性が増して、巣全体が完成に向かって加速する。
この研究、ものづくりや工学だけでなく、私たちの挑戦や成功のプロセスにもそのまま応用できるような気がしてなりませんでした。
最初のバラバラが、やがて「構造」になる
鳥の巣の初期段階のように、私たちの挑戦も、最初は失敗と不安定の連続です。
一つの作業、一つの判断、どれも手応えがなくて、何をしているのかすら分からない。
でも心理学者ソーンダイク(Edward L. Thorndike)の「試行錯誤学習」のように、一見ムダに見える繰り返しが、実は無意識下で“問題解決パターン”を蓄積しているといいます。
つまり、最初の“できない時期”こそが、その後の飛躍の土台になっているということ。
失敗しては崩れ、また積んで・・という過程の先に、私たちの中で「自己組織化(self-organization)」が起き始めます。
これが、経験の蓄積によって脳がパターンを認識し始め、やがて複雑な問題に対しても直感的に対応できる状態になるという成長フェーズです。
そしてこの“しきい値”を越えた先には、非線形な成長が待っています。
それまでの遅々とした進みが嘘のように、スピードと成果が一気に加速する瞬間。これは学習や技術習得だけでなく、ビジネスの場面でも同様に見られる現象です。
成功とは、「壊れにくい構造」になっていること
もちろん、最初からスムーズに成功する人もたくさんいます。
でも、私たちが外から見て「成功している」と思う人の中には、その裏で何度も試行錯誤を繰り返してきた人も少なくありません。
むしろ、あまりにも早く成功したケースほど、構造が脆く、崩れるのも早いというのもまた事実です。
だからこそ、挑戦の初期に起こる失敗は、ただの“つまづき”ではなく、「構造をつくるための素材集め」なのだと考えてみてほしいんです。
私たちが今直面している試行錯誤――それは、自分だけの“鳥の巣”を作り上げている最中かもしれません。
というわけで、今回は「鳥の巣」をヒントにした、試行錯誤と成功の構造について書いてみました。
最初に崩れた枝にも意味がある。
うまく噛み合わなかった一歩にも、価値がある。
そう思えたら、少しだけ前向きに、また一歩を積み上げられる気がしませんか?
それでは、また次の記事でお会いしましょう!